| 要望(1) |
【要 望】弁理士の質を将来にわたって確保・維持するため、早急に単なる「量」から「質」重視への政策転換を行なうこと。平成12年度から10年間にわたり行われ続けた弁理士試験合格者の大幅増員を見直すこと。
【具体策】1.平成22年度弁理士試験から「合格基準」を引き上げ、合格者を順次抑制すること(短期的要望)。 即ち、平成20年度合格者数(500名程度)から順次減少させること。
2.弁理士試験の適正化を図るため、これまで簡素化された弁理士試験制度の見直し(免除と試験
科目等)と、そのための検討を早急に行なうこと(中期的要望)。
【所 管】経済産業省特許庁・工業所有権審議会弁理士審査分科会
|
(理由)
前政権下における行き過ぎた規制緩和政策により弁理士試験の簡素化が繰り返され、過去10年間にわたって弁理士試験合格者の大幅増員(平成21年度弁理士試験合格者数813名、平成20年度は574名、実に前年比41.6%増)が行なわれた。弁理士数はここ10年間で倍増し、既に8,600人を超えている。一方、経済状況の急激な悪化と長期の景気低迷にともない国内特許・実用・意匠・商標の出願件数は減少の一途をたどっている。このため弁理士にとって必要不可欠な実務経験を十分積む機会が急激に減少し、このままでは将来にわたって弁理士の質の確保・維持が困難になりつつある。一方で、料金設定などについて企業側の要請が強く働き価格破壊現象が表面化している。当然、弁理士一人当たりの出願件数は2001年以降減少の一途をたどっている。10年来の弁理士試験合格者の大幅増員により弁理士有資格者数は年々増加が続いたことから、ベンチャー・中小企業支援を担う弁理士の報酬は顕著に低下し事務所の経営環境は厳しい状況に直面している。この結果、弁理士資格の魅力が低下し、期待する人材が集まらない、という悪循環に陥っていることは明らかである。知的財産の分野では技術の高度化、特許要件等の厳格化、国際的な視点での業務処理の必要性の増加等が相まって、業務処理に要する能力・労力は以前とは比較にならないほど高まっている。高度な専門性を必要とする国家資格には、その取得に対して高いハードルを課するのは当然であり、安易に緩和すべきではない。
(補足)金融庁の公認会計士・監査審査会は、2009年の公認会計士試験合格者が前年比38.5%減少と発表。
政府は、司法試験において閣議決定されている「年3000人合格目標」を下方修正する方向で見直す方針との報道。 |
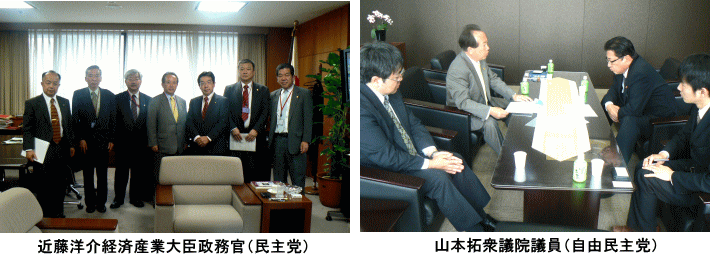 |
|
| 要望(2) |
【要 望】3月30日に公表された「知的財産推進計画2010の骨子」の中の4頁の次の項目、『ベンチャー・中小企業に対する特許関係料金の減免制度を拡充する。また、特許出願に不慣れなベンチャー・中小企業のための出願支援策として、弁理士費用の負担を軽減させるための方策(例:「特許パック料金制度」(特許庁へ支払う費用と弁理士費用を合わせた低額な料金制度) )やその是非について関係者の意見を聞きつつ検討を行い、2010年度中に結論を得る。(短期)』の中の下線部について、弁理士に負担を強いるような施策であるならば、到底容認することはできません。特に「特許パック料金制度」については、弁理士手数料に多大な悪影響を及ぼす可能性があるので、その是非について弁理士(日本弁理士会)の意見を十分尊重すること。
【具体策】ベンチャー・中小企業のための出願支援策としては、特許関係料金、特に出願審査請求料の引き下げ(半額程度)を行なってベンチャー・中小企業の負担を軽減させることが適当である。万が一「弁理士費用の負担を軽減させるための方策」を検討する場合には、ベンチャー・中小企業に対し弁理士手数料の公的助成・補助を行って対応すること。
【所 管】知的財産戦略本部・内閣官房知的財産戦略推進事務局
|
(理由)
平成12年度から10年来の弁理士試験合格者の大幅増員による弁理士有資格者数の増加と日本経済の長期低迷による国内特許出願件数の減少により、今弁理士業界を取り巻く環境は最悪の状況にあります。また、殆どが1人・2人事務所(全体の82%を占める)という小規模経営の弁理士および特許事務所に、国が行うべきベンチャー・中小企業支援の過大な負担を強いて事務所経営を圧迫するような施策は、到底容認することはできません。また、弁理士手数料を低額な料金に固定化するという特許パック料金制度は、弁理士業務の質の低下を招く恐れがあります。ベンチャー・中小企業の知財戦略を根底から支えている弁理士の業務に対するインセンティブを低下させるような施策は、愚かであるといわざるを得ません。
特許庁は平成15年に「特許法等の一部を改正する法律」の改正を行い特許料及び特許出願料を引き下げた一方で、適正な審査請求行動を促進するためとして出願審査請求料を約2倍に引き上げました。国内特許出願件数が減少している今となっては、出願審査請求料をもとに戻し、日本の知財パワーを取り戻すことこそ、最も時宜を得た施策と考えます。
知的財産立国を標榜する我が国にとって知的財産権化は最優先の課題のはずです。国が成長戦略の一環として十分な予算を計上し、ベンチャー・中小企業の知的財産権化を全面的に支援することこそ、日本経済再生の本道と考えます。
(補足)知的財産戦略本部では、本骨子を基に議論をさらに深め、本年5月を目途に「知的財産推進計画2010」を策定。知財の創造、保護及び活用に関する重要事項の検討、施策の進捗管理を政治主導で実施するため、企画委員会(構成員は座長として国務大臣、委員として国家戦略室及び内閣府、文部科学省、経済産業省の副大臣又は大臣政務官)を設置。
|
 |
|
| 要望(3) |
【要 望】法務省が臨時国会に提出方針と報じられた「弁護士法人法案(仮称)」は、外国法事務弁護士の日本での法人設立を認め、日本での活動を大幅に緩和(容易)するものである。日本弁理士会は、弁理士業務に多大な悪影響を及ぼす恐れがある本法案には「反対」である。我々の懸念が解消されるまで、容認することはできない。
【具体策】法務省は、本法案の法制化には慎重に対応すること。日本弁理士会の意見を、十分尊重すること。
【所 管】法務省・司法法制部
|
(理由)
「弁護士法人法案(仮称)」は、外圧を受けて外国法事務弁護士の日本での活動を緩和するという方針に基づいて、前政権が規制緩和の一環として推進してきた施策の一つです。本法案の要点は、これまで日本国弁護士にしか認められていなかった法人設立を「外国法事務弁護士」と「日本国弁護士と外国法事務弁護士との共同」にも認めるというものです。弁理士は、“日本国特許庁に対する出願代理業務”、“外国から日本国特許庁に対する出願代理業務”、“外国出願関連業務”を主な仕事としています。我々は、①外国法事務弁護士の法人設立を認めることにより、外国法事務弁護士の活動エリアが大幅に拡大し、巨大な外国資本を背景とするローファームのような大規模事務所の日本進出を加速させることになるのではないか、②弁護士法第3条第2項に「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行なうことができる」という規定があるため、日本国弁護士と外国法事務弁護士との共同法人を設立することによって弁理士業務も行なうことが可能になるのではないか、という懸念を持っています。要するに、外国法事務弁護士の日本での活動を大幅に緩和させるということは、弁護士はもとより国際性が強く外国出願関連業務のウエートが他士業に比べて高い弁理士にも多大な影響を及ぼす、ということを法務省は理解して頂きたい。4月13日の日本経済新聞「外国弁護士活動容易に、法務省方針」の記事が掲載されてから、日本弁理士会には弁理士会員から不安の声、懸念の声が多く寄せられています。外国法事務弁護士については、日本弁護士連合会が直接対応すべきものと承知はしていますが、多くの弁理士会員から懸念の声がある以上、日本弁理士会としても本法案の成り行きを看過することはできません。
万が一、法務省が本法案の国会提出を行う場合には、弁理士に対する資格の相互承認がない以上外国法事務弁護士については、弁理士の業務である全ての外国出願関連業務は除外する等についても考慮に入れるよう検討することを要望します。
(補足)法務省は、「外国弁護士制度研究会報告書(平成21年12月24日公表)」の内容に基づいて、弁護士法人法案(仮称)を早急に法制化したい意向。早ければ秋の臨時国会に提出する方針。
|
|

