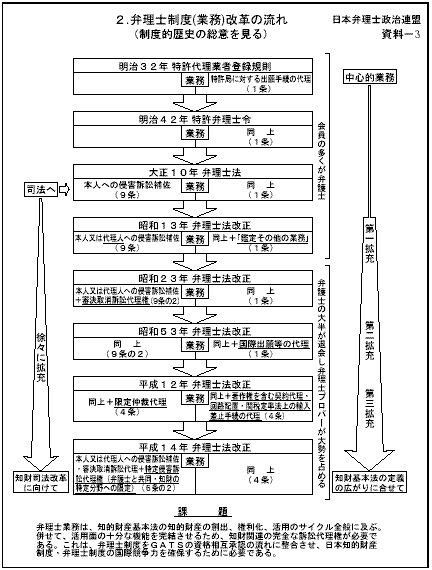 |
俁丏曎棟巑惂搙夵妚偺寛抐偼媞娤揑憤堄偱乮帒椏乕俁乯
乮1乯媞娤揑憤堄偲偼
丂愭偢偼丄楌巎偵棤晅偗傜傟偨幮夛偺僯乕僘丄師偵丄楌巎偵棤晅偗傜傟偨曎棟巑偺憤堄偑嫇偘傜傟傞丅偙傟傜傪丄乽曎棟巑惂搙乮嬈柋乯夵妚偺棳傟乿偺僠儍乕僩偵昞偟偨丅
丂偲傝傢偗丄乽曎棟巑偺憤堄乿偵偮偄偰偼丄尰嵼偺曎棟巑偺栚偐傜尒偨庡娤揑側傕偺傛傝偼丄楌巎偵愊傒忋偘傜傟偨憤堄傪媯傒庢傞偙偲偑娞梫偱偁傞丅壗屘側傜偽丄変乆抦嵿偺愱栧壠偼幚柋壠偱傕偁傞偐傜丄偲偐偔栚愭偺僥僋僯僇儖側懁柺偵婥傪庢傜傟丄曎棟巑惂搙傪庢傝埻傓娐嫬偺曄壔偵婥晅偐偢懢嬌傪尒幐偆孹岦偵偁傞丅
偦偺偨傔偵丄夛堳偼杮夛惓暃夛挿夛偺曽乆傪慖嫇偱慖傃丄僋儕僥傿僇儖側敾抐丒寛抐傪晅戸偟偰偄傞偺偩丅惓暃夛挿夛偺傗傞偙偲偼寛傑偭偰偄傞丅偙偺僠儍乕僩偺巜岦偡傞愭偺寛抐傪偡傞偙偲偱偁傞丅
乮2乯偙偺僠儍乕僩偵傛傞偲丄杮棃偺嬈柋傕巌朄暘栰偺嬈柋傕丄幮夛偺僯乕僘偵懳墳偟偨曎棟巑偺擬怱側梫朷偵傛傝彊乆偵奼戝偟偰偒偨偙偲偑敾傞偑丄摿昅偡傋偒偼丄曎棟巑偺巌朄暘栰傊偺嶲擖婜偑戝惓侾侽擭偲丄杮棃偺嬈柋奼廩偺戞堦抜奒偺徍榓侾俁擭偵偐側傝愭傫偠偰偄偨偙偲偱偁傞丅
係丏抦揑嵿嶻婎杮朄偺崙嶔傪姰慡偵巟偊傞曎棟巑惂搙傊
丂丂( 帒椏乕係乯
乮1乯愭偢曎棟巑朄偺栚揑偲曎棟巑嬈柋傪抦揑嵿嶻婎杮朄偵惍崌乮崙嶔惍崌乯
丂抦揑嵿嶻婎杮朄偼丄偦偺戞俀忦偱乽抦揑嵿嶻乿傗乽抦揑嵿嶻尃乿偺掕媊傪偟偰偄傞丅偙傟傜偺掕媊偼丄偄傢備傞乽抦揑嵿嶻乿傪憂憿偝傟偨乽忣曬乿偲偟偰懆偊偰棯栐梾揑偲偄偊傞峔偊偵側偭偰偄傞丅
丂偟偐偟側偑傜丄曎棟巑朄偱婯掕偡傞曎棟巑朄偺栚揑乮戞侾忦乯傗丄曎棟巑嬈柋偼丄揱摑揑側昞尰乮椺偊偽乽岺嬈強桳尃乿乯偺拞偵巭傑傝丄傑偨丄摿嫋挕娭學偺嬈柋偑拞怱偲側傝丄懠偺抦揑嵿嶻偼婑偣栘嵶岺揑偵婯掕偝傟偰榗乮偄傃偮乯側傕偺偵巭傑偭偰偄傞丅
乮2乯師偵巌朄暘栰偱偺婡擻傪姰慡壔乮儐乕僓乕僼儗儞僪儕乕側惂搙偵乯
丂晅婰曎棟巑惂搙偑暯惉侾係擭偐傜僗僞乕僩偟偰丄帋尡偵崌奿偟偨曎棟巑偵偼丄乽曎岇巑偑庴擟偡傞帠審乿偵尷傝丄偟偐傕乽摿掕怤奞慽徸乿偺斖埻偱慽徸戙棟尃偑晅梌偝傟偨偑丄偙傟偼丄幚幙揑偵廬棃偺慽徸曗嵅偲堎側傞偲偙傠偑側偄丅偄偭偰傒傟偽愑擟偺傒偑戙棟恖偲摨偠偲偄偆丄曎岇巑惂搙偺廬懏惂搙偲偟偰幚尰偟偨丅偦傕偦傕丄偙偺傛偆側曎岇巑惂搙偺鏱乮偔傃偒乯壓偵偁傞惂搙偼丄幮夛傕変乆偺愭攜払傕憐掕偟偰偄側偐偭偨丅
丂傑偨丄巌朄暘栰偵偍偗傞偦偺偐偨偪偺榗偝偼丄杮棃偺嬈柋偲懳斾偡傞偲峏偵憹暆偟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂偦傟偱傕丄変乆曎棟巑払偺懡偔偼丄尓嫊偵庴偗巭傔偰擔乆偺嬈柋偺拞偵曌嫮偟側偑傜晅婰曎棟巑偺庴尡偵僄僱儖僊傪孹拲偟偰偄傞丅傑偙偲偵戝曄側偙偲偱偁傞偑丄偦傟偼丄嬤偄彨棃丄抦揑嵿嶻偵娭偟偰曎棟巑偑姰慡側慽徸戙棟偑偱偒偰丄曎棟巑惂搙偑丄巌朄暘栰偵偍偄偰傕儐乕僓乕僼儗儞僪儕乕側惂搙偲側傞偙偲傪柌偵昤偄偰偄傞偐傜偱偁傞丅
丂曎岇巑偲偺嫟摨偼丄慽徸偺婯柾傗撪梕偵傛傝儐乕僓乕偺慖戰偵埶傜偟傔傞偺偑丄杮棃偺戙棟恖惂搙偺偁傞傋偒偡偑偨偱偁傠偆丅 |
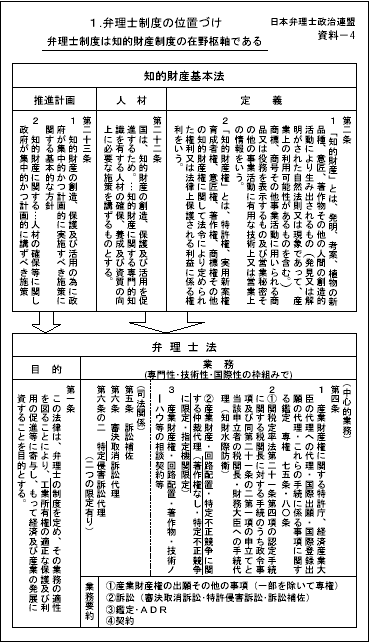 |
俆丏乽朄棩偲媄弍偺愱栧壠乿偺榞慻傒峔抸乮帒椏乕俆丒帒椏乕俇乯
丂尰嵼偺曎棟巑帋尡惂搙偼丄朄暥宯偺慺梴偟偐扴曐偝傟偢偵曎棟巑偲側傞幰偲壢妛媄弍偺慺梴偟偐扴曐偝傟偢曎棟巑偵側傞幰偑攜弌偝傟傞巇慻傒偲側偭偰偄傞丅偙傟偱偼丄屄乆偺曎棟巑傪嵦偭偨応崌丄乽朄棩偲媄弍偺愱栧壠乿偱偁傞偲偼偄偊側偄偟丄偟偨偑偭偰丄抦揑嵿嶻偺榞慻傒偵懳墳偟偰偄傞偲偼偄偊側偄丅摨帪偵丄曎岇巑傗懠巑嬈偵懳偡傞惂搙揑側傾僀僨儞僥傿傕柧妋偱偼側偄丅
擛忋偺偙偲傪摜傑偊偰曎棟巑惂搙傪恀偺乽朄棩偲媄弍偺愱栧壠乿偺惂搙偵夵妚偡傞偨傔偺梫掹偼丄嘆曎棟巑帋尡偺摿偵帋尡壢栚偺夵掕丄嘇尋廋偺搊榐梫審壔丄偦偟偰嘊僾儘僙僗嫵堢曽幃偺摫擖偵偁傞丅
乮1乯僾儘僙僗嫵堢曽幃偺摫擖偺惂搙栚揑
丂丂庴尡丄尋廋幰偺晧扴傪帪娫幉忋偱暘嶶寉尭偟丄懡條側恖嵽傪曎棟巑惂搙偵桿場偡傞偙偲偱偁傞丅
乽朄棩偲媄弍偺愱栧壠乿偺榞慻傒偱峔抸偝傟傞乽悽奅堦偺嫞憟椡偱柌偺偁傞曎棟巑惂搙乿偼丄偲傝傢偗榑暥帋尡偺帋尡壢栚偵丄朄棩偲帺慠壢妛宯壢栚偑昁恵偲偟偰擖傞偙偲偵側傞丅偟偨偑偭偰丄帋尡偺儗儀儖偑崅偔側傝丄庴尡幰丄尋廋幰偺晧扴偼戝偒偔側傞偑丄柌偑晧扴傪忋夞傟偽嶲擖幰偑尭傞偙偲偼側偄丅
丂傑偨丄帋尡丄尋廋偼晧扴偑戝偒偄偙偲偵堄枴偑偁傞偺偱偼側偄偐傜丄儗儀儖傪堐帩偟偨傑傑庴尡幰丄尋廋幰偺晧扴傪寉尭偱偒傟偽丄偦傟偵墇偟偨偙偲偼側偄丅偦偺寉尭庤抜偑僾儘僙僗嫵堢曽幃偱偁傞丅
丂偦傟偼丄椺偊偽丄庴尡慜偵朄棩壢栚偲帺慠壢妛宯壢栚偺扨埵傪戝妛傗愱栧妛峑偱庢摼偡傞偐丄偁傞偄偼偦偺儗儀儖偺嫵堢婡娭傪懖嬈偡傞偙偲傪忦審偵庴尡壢栚偺柶彍偺惂搙傪愝偗傞偙偲偱偁傞丅
乮2乯帋尡偺惂搙栚揑
丂乽朄棩偲媄弍偺愱栧壠乿偺榞慻傒偱婯掕偝傟偨曎棟巑偲偟偰偺乽慺梴乿傪扴曐偡傞偙偲偱偁傞丅偁偔傑偱傕丄乽慺梴乿偺扴曐偱偁偭偰丄乽懄愴椡乿偺扴曐偱偼側偄丅
丂帋尡偼丄抁摎幃丒榑暥幃丒岥弎幃偺嶰抜奒偲偟丄摿偵丄嶻嬈嵿嶻朄丄忦栺椶丄柉帠慽徸朄丄帺慠壢妛宯壢栚傪榑暥帋尡偺昁恵偲偡傞偙偲偑娞梫偱偁傞丅柉帠慽徸朄偲帺慠壢妛宯壢栚傪慖戰偵偟偨偺偱偼廬棃偲堎側傜偢丄夵妚偵偼側傜側偄丅
乮3乯尋廋偺惂搙栚揑
丂曎棟巑偲偟偰嵟掅昁梫側乽懄愴椡乿偺扴曐偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄偙傟偼丄曎棟巑搊榐偺梫審壔偺夵妚傪敽偆丅
丂偁偔傑偱乽懄愴椡乿偺扴曐偑庡偨傞栚揑偱偁傝丄乽慺梴乿偺扴曐偼丄曗廩揑偵憐掕偡傞偙偲偑偱偒傞壢栚偵尷傞傋偒偱偁傞丅偲傝傢偗丄帺慠壢妛宯壢栚偼尋廋偵側偠傑側偄丅
丂尋廋壢栚偼丄椺偊偽丄弌婅幚柋丄椶斲丒堎摨敾抐丄柉朄丄奜崙抦嵿朄側偳偱偁傝丄帺慠壢妛宯壢栚偼抁偄尋廋婜娫偱偼偦偺栚揑傪払惉偱偒側偄偼偢偱偁傞偐傜丄憐掕偡傞傋偒偱偼側偄丅 |
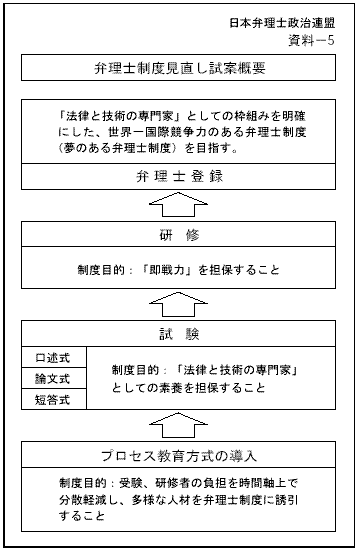 |
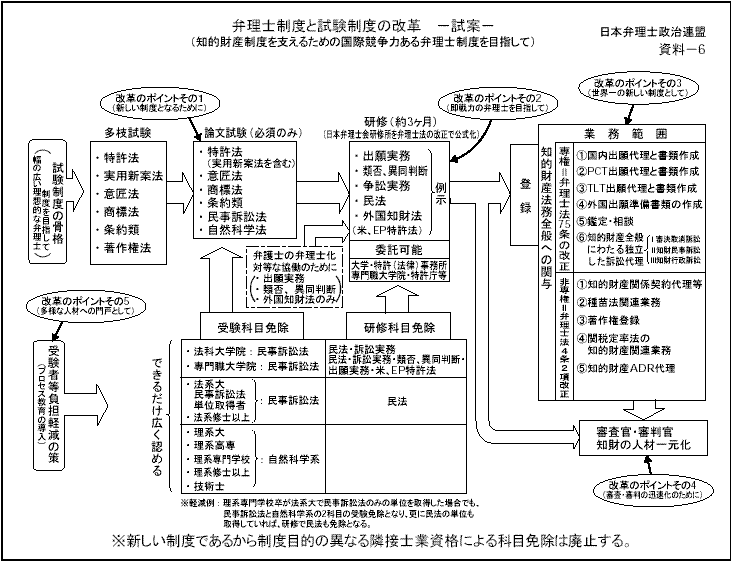 |
俇丏桪愭弴埵傪偮偗傞側傜偽乮寢榑乯
丂摿偵丄帒椏乕俇偵丄乽悽奅堦偺嫞憟椡偱柌偺偁傞曎棟巑惂搙乿偺慡懱憸傪丄徻嵶偵帵偟偰偁傞丅
丂偙傟偼丄抦揑嵿嶻偺暘栰偺慡偰偵媦傇姰慡側慽徸戙棟尃傪娷傓曎棟巑偺嬈柋斖埻偲丄曎棟巑偵側傞僾儘僙僗傪帵偡僼儘乕僠儍乕僩偱偁傞丅
丂偟偐偟側偑傜丄悽偺拞偺忢偲偟偰丄堦婡偵帠傪恑傔傞偙偲偼擄偟偄丅偦偙偱丄嵟廔栚揑傪払惉偡傞偨傔偵丄夵妚偺桪愭弴埵傪晅偗側偗傟偽側傜側偄丅
丂偦傟偼丄嘆榑暥帋尡壢栚傪昁恵偺傒偵摑堦偟丄
丂丂丂丂丂嘇忦栺椶傪暅婣偝偣丄
丂丂丂丂丂嘊柉帠慽徸朄偲帺慠壢妛宯壢栚傪壛偊傞丄
偙偲偱丄乽朄棩偲媄弍偺愱栧壠乿偲偟偰偺曎棟巑偵昁梫側嵟掅尷搙偺乽慺梴乿傪扴曐偡傞扨弮柧夝側帋尡惂搙偲偟丄
丂丂丂丂丂嘍尋廋傪搊榐梫審壔偟丄
丂丂丂丂丂嘐尋廋偱偼丄椺偊偽丄弌婅幚柋丄椶斲丒堎摨敾抐丄憟徸幚柋丄柉朄丄奜崙抦嵿朄傪棜廋偡傞傕偺偲偟丄曎棟巑偲偟偰嵟掅尷搙昁梫側乽懄愴椡乿偺扴曐偲丄乽慺梴乿偺曗廩傪峴側偄丄
丂丂丂丂丂嘑僾儘僙僗嫵堢曽幃偺摫擖偱丄榑暥帋尡偺柉帠慽徸朄丄帺慠壢妛宯壢栚偺庴尡柶彍丄尋廋偺揔摉偲偝傟傞壢栚偺棜廋柶彍傪丄偱偒傞偩偗峀偔懳徾幰偵懳偟偰峴側偆丄帋尡丒尋廋惂搙偺夵妚傪愭偢峴側偭偰丄姰慡側慽徸戙棟尃傪娷傓嬈柋斖埻偺夵妚偺慴傪抸偔偙偲偲偡傞丅
丂偄傑丄杮夛偼丄寽柦偵帋尡惂搙夵妚偺撪梕傪専摙偟偰偍傜傟傞丅懡偔偺堄尒偑嶖憥偟偰揨傔傞偼崲擄偱偁傠偆偲巚偆偑丄偙偙偱丄媞娤揑憤堄偵婎偯偒寛抐傪偡傞帪婡偵偒偰偄傞丅
丂曎惌楢偼惌帯揑懁柺偐傜娐嫬惍旛偵搘椡偟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅 |
| 埲忋 |
|
